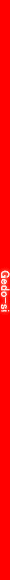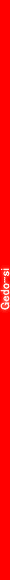
第七話「笑う影」
―2―
|
背凭れの可動範囲ギリギリまで椅子に体を預け、両脚を机の上に置いたいつもの寛ぎスタイルで新聞を広げていたオレは、とうとう我慢出来なくなって吐き捨てた。 「つまらん」 独り言とは全く重症だが、実際に暇を持て余しているのだから仕方ない。 しかし厄介な事に、口に出してしまうと余計に苛々がつのった。 九鬼霊障相談所。 表向き掲げている看板からして胡散臭いこの事務所に、その手の仕事が舞い込んでくる事はまず無かった。仮に、何かの間違いで客が迷い込んで来たところで、オレの顔を見ればその場で回れ右するのが関の山。まったく失礼な話だが、営業スマイルの一つも覚えないオレが文句を言えた義理では無いし、そもそも下らない身の上相談やら被害妄想に付き合う気は毛頭無いので、一々追い返す手間が省けると言う点では寧ろ好都合だった。 まぁ、一事が万事その調子なので、収入と言えば裏の――そして本来の仕事である(月数件あるか無いかの)退魔業のみ。尤もそちらは法外な料金を吹っかけているので、仕事が少なくても生活に困ることは無い。 困ることは無いのだが、それはそれで別の問題を孕んでいた。 それはもう、独り言で悪態を吐きたくなるほどに。 日が西に傾き始めた土曜の午後。点けっ放しのテレビから流れるのは再放送の番組ばかり。何か面白い記事でも無いものかと眺めていた新聞は丸めてゴミ箱の中。灰皿の上には吸殻が山盛りで一つのオブジェと化しているのも、退屈な日常そのものの光景だった。 「久しぶりに、やるか」 待てど暮らせど何も起きないのなら、自分から動くしか無い。そう思い立ち、外出の準備を始めたところで突然、派手な音を立てて事務所のドアが開いた。何事かと振り返れば、視線の先には少女が一人。どうやらかなり急いでいたらしく、髪も服も乱れたまま肩で息をしているその娘は、オレの姿を認めるなり開口一番こう言った。 「お願いです!小春ちゃんを――お姉ちゃんを助けてください!」 「…………ハァ?」 鏡を見るまでもない。 その時のオレは、これまでの人生でも五本の指に入る程の間抜け面を晒していただろう。 ◇ 招かれざる客とは言え、無下に扱う訳にも行くまい。 いや、これが不細工な小娘だったならボコボコにして蹴り出していたところだろうが、幸いと言うべきか、なかなか綺麗な顔立ちの娘ではあったし、さらに言えば少々気になる事もある。 オレは手にしていたコートをハンガーに戻すと、玄関に突っ立ったまま捨てられた子犬のような目をした娘をソファに座るように促した。接客らしく茶でも出そうかと思ったが、生憎とこの事務所にそんな気の利いた物がある訳も無く。仕方無しに冷蔵庫を開けてみると缶コーヒーが何本か転がっていたので、適当に一本取り出し無造作に放り投げた。 あ、と思った時にはもう遅い。 緩やかな放物線を描いた缶コーヒーは、完全に反応が遅れた娘の目の前を通り過ぎて床に激突、そのまま部屋の隅まで転がると、壁にぶつかって漸く止まった。 「え、あの……ご、ごめんなさい」 別に、謝らんでも。 何だか背中がムズ痒くて堪らん。 「まぁ……その、何だ?とりあえず、話だけでも聞こうじゃねぇか」 得体の知れぬムズ痒さを何とかやり過ごしたオレは、向かいのソファに腰を沈め、改めて娘を観察する。 まず目に付くのは、大きく二房に束ねられた長い亜麻色の髪。頭頂部から肩口まではサラサラと流れるように、しかし肩口から胸の前に垂らした二房はフワリと柔らかなウェーブを描き、そのボリュームに反して重さを感じさせない様は綿毛を連想させる。未だ緊張した面持ちではあるものの、垂れ気味の大きな瞳から受ける印象は全体的におっとりしていて、アナクロな黒縁眼鏡と相まって生真面目で垢抜けない印象を受ける。 大きなカラーが目を引く服は、名前は忘れたが確かこの辺りの私立学校の制服だったはず。スカートの長さは今時珍しい膝下そこそこ、つまりクソ真面目に校則を守っているのだろう。学校指定と思われる味気無いデザインの鞄にキーホルダーの類が幾つかブラ下っている他は、目立った装飾品も見当たらない。 良く言えば品行方正、悪く言えば地味、と言ったところか。 しかし、見た目ほど大人しい性格とも思えない。むしろ無鉄砲と言えるほどの行動力を備えていると、そう断言できる。でなければ、今この時点でオレの目の前に座っているはずが無い。 『日向野日和』と名乗った娘は、おずおずと語り始めた。 双子の姉『小春』のこと。 その姉の行動が近頃不審であること。 そして、最近学校で起きている一連の事件のことを。 「夜になると小春ちゃん、一人でフラっと出掛ける事があるんです。朝には家に帰って来てるんですけど、どこに行ったか聞いても教えてくれないし……それに、小春ちゃんが出掛けた次の日には、学校の誰かが行方不明になってるんです。今日も、小春ちゃんのクラスの担任の先生が、居なくなったって噂になってて……」 そう話している間にも日和は涙声になってくる。 「こっ……小春ちゃんも、何か事件に、ま、巻き込まれてるんじゃ……ないかって、心配で、心配でぇ……」 あぁ、とうとう泣き出しやがった。どうもこの娘の相手をしていると調子が狂う。やり辛くて仕方ない。やはり最初に蹴り出しておくべきだったかと後悔しかけたが、彼女の話に興味が無いと言えば嘘になる。 「よし、話は大体分った。オレが調べてやる」 「ホントですか!!」 沈んでいた顔が途端にぱぁっと明るくなった。だから、そんな眼でオレを見るなって。 「ああ。その話、オレも興味がある」 どうせ暇だったし、とは言わない。 「それで――だ。報酬についてだが……」 その言葉を聞いて日和は「あっ」と叫んだ。キラキラ輝いていた顔が一転して、見る見る暗く沈んでゆく。まったく、忙しい娘だ。 「オレも慈善事業でこの仕事をやってるワケじゃぁないからな」 「あの、今はそんなにお金持ってませんけど、バイトとかして、必ず払いますからっ!!私に出来る事だったら、何でもしますから、だからっ!!」 何でもします――と来た。思わず顔がニヤケるのを堪えつつ、内心ほくそえむ。やっとこっちのペースに引き込めそうだ。 「何でもする、か。なら報酬は――身体で払ってもらおうか?」 「からだ……ですか?」 「ああ、学生が稼いだ金なんて高が知れてるしな。なら身体で払ってもらった方がいい」 「は……はいっ、分りました!私、一生懸命頑張ります!!」 一体、何を頑張るつもりでいるのか、この娘は。多少……いや、かなり互いの意志疎通に齟齬があるようだが、了承さえ取ってしまえば問題無い。後で泣こうが喚こうが、こちらの知った事では無い。 ――むしろ泣いて喚いてくれた方が、興が乗るってモンだ。 「交渉成立だな。それじゃあ早速だが、その姉さんとやらに会わせてくれ。時間が惜しい。それと、出来ればあまり人目に付かない場所の方が良いな」 「あ、は、はい!分りました」 事件の詳細は道々聞く事にして、外出の準備を始めたオレは、ふと心の隅に浮かんだ疑問をぶつけてみる事にした。 「ところで、一つ聞きたいんだが」 「はい、何でしょう?」 「普通、この手の話は警察、それがダメなら探偵なりに相談するモンじゃねぇのか?何でオレのところに?」 「え?」 何を言ってるのか分らない、と言った顔で娘が答た。 「だって、探偵屋さん――ですよね?」 ……ダメだ、暫く自分のペースは取り戻せそうにない。 ◇ 日和が姉を呼び出すのに指定したのは、街外れの廃工場だった。確かに人目に付かない場所がいいとは言ったが、この娘、ちょっと……いや、かなりズレている。 時刻は夕暮れ時。太陽が徐々に地平線に沈んでいく中、相手が現れるのをじっと待つ。その間にオレは考えを纏めていた。 この娘は、姉が事件に巻き込まれているかも知れないと言っていたが、それは間違いだろう。恐らく彼女自身が主犯格、さらに言うならばコレは十中八九、妖魔絡みの事件だ。 殆ど勘と経験則で導き出した結論だが、根拠もいくつかある。まず人間の犯行だと仮定した場合、学校という限定された範囲内での連続誘拐・監禁・殺害等は足が付き易くリスクが大きいし、何より露見するのが早い。現時点でまだ警察が動いていない事も考えると、通常の事件であるとは考え難い。単に失踪や家出が偶然続いたと考えられなくも無いが、少々強引な感は否めない。しかし、これが校内に潜んでいる妖魔、もしくは学校に出入りしている人間に取り憑いた妖魔の犯行と考えると、良い具合に型に嵌る。それに―― そわそわと落ち着き無い様子の日和を、横目で盗み見る。 一見するとただの女子高生、何の異変も違和感も無いが、だがオレの右目は彼女に纏わり付く妖気の残滓を確かに捉えていた。 ――それに、この濃度の妖気を纏っている娘に憑いていないとなると、後はかなり限定されるからな。 そんな事を考えているうちに、待ち合わせの相手が廃工場の入口に現れた。双子と言うだけあって顔立ちは似通っているが、受ける印象はまったく違う。肩のあたりで切り揃えた短めの髪や、制服の着こなし方一つ取っても彼女の活発さがにじみ出ていて、実に対照的な双子と言える。 「ねぇ、日和?何なの、こんな所に呼び出して……それに、会わせたい人って、その人?」 沈む太陽を背にして工場内に入ってきた少女と目が合った、その瞬間、オレの右目は彼女の中に潜む妖気を捉える。間違い無い、コイツはクロだ。 「成る程、『影渡り』か。道理で男ばかり消えるわけだ」 「……何?まさか、お前……」 いきなり名を呼ばれた『ヤツ』の動揺が手に取るように分かった。口元に自然と嘲笑が浮かぶ。 「その、まさかさ」 『天敵』の出現を察した『ヤツ』はアッサリと化けの皮を脱いだ。少女の口から、とても彼女のものとは思えない耳障りで甲高い声が洩れ出す。 「やっぱり、最初に家族を始末しなかったのは失敗だったかしら?」 「え?何、言っているの?小春ちゃん」 恐らく未だかつて聞いた事が無いであろう物騒な物言いに、日和が目を丸くする。姉の身に何が起きているかなど知る由も無いのだから、当然の反応ではあるが。狼狽える娘を横目に、オレは軽口を叩きながらも油断無く『ヤツ』の隙を窺う。今さっき気付いたとは言え、『影渡り』を相手にこの時間、この場所、この位置関係を選んでしまった事は、明らかな失態だった。 「そうでも無ぇさ」 「そう?」 「家族が消えて、一人だけ残れば悪目立ちもいいトコだ。失敗っつーなら、まず憑く人間から間違いだ。どうせなら親しい人間が居ないヤツを選ぶべきだったろうが――まぁどっちにしろ、狭い範囲で立て続けに事件を起こせば周囲の注目を浴びるのは当然だし、『網』に掛かるのも時間の問題。堪え性が無いのが災いしたってワケだ」 「成る程ね、有難う。参考になったわ」 「礼は要らねぇ。それより、さっさとその身体から出て行けよ。お前の始末までは依頼にゃ入って無ぇんだ、今回はな。今ならまだ見逃してやるぜ?」 「ケッ、ケケケケケッ!!」 妖魔に憑かれた少女が、嫌な声で笑う。いや、少女だけではない。西日を受けて長く伸びた影の、その頭の部分が三日月のように裂け、ケタケタと声を上げて笑う。 『ケケケケケケケケケッ!!見逃すだぁ?馬鹿言ってんじゃねぇや、オレはこの身体が気に入ってんだよぉ!』 「仕方無ぇ……なら、力尽くで叩き出すまでだ」 同時、懐から呪符を取り出し発動に入る。 『ケケケッ!やれるモンならなぁッ!!』 |
外道士TOPへ