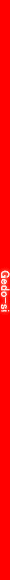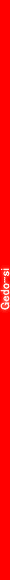
第七話「笑う影」
―1―
|
「ねぇ、先生?」 仄淡く照らされた、モノクロームの世界の中で 妖しく微笑む、白い少女。 ――これは、夢だろうか? そう それは、あまりにも 現実味に乏しい光景だった。 ◇ 深夜の学び舎。 「ったく、何で今どき宿直なんか……こんなのは警備会社にでも任せておけば……」 その日、宿直当番となった彼はブツブツと独り呟きながら校舎を見回っていた。 いや、腰の引けた頼りない足取りやキョロキョロと落ち着かない目線、全体的に挙動不審なその様子は、宿直の見回りと言うよりはむしろ、不法侵入者のそれではあったが。 夜は暗い 夜は静か 夜は寂しい 昼間の喧燥とは打って変わり、深い海の底に沈んでしまったかのように、暗い静寂に包まれた広大な空間。微かに聞こえる幻聴は――否、通りを走り去る車の音か。 まるで、今この時、この場所だけが世界から取り残され、隔離されてしまったかのような。 異界さながらの、名状し難い不気味な雰囲気。 もしや、この世界では己こそが異物なのではないか―― そこまで考えて男は頭を振った。 ――そんな馬鹿な話、あるわけ無いじゃないか。 不安のあまりあらぬ妄想を膨らませる己を戒めながら、校内の見回りを続ける。 ふと窓から外を見れば、青白く染まった中庭が見えた。 随分と――恐らく校内よりは――明るい。月が出ているのだろうか。 こうして見ると、海の中にでも居るようだ。 半ば呆けたように外の世界に見惚れていた、その時。 視界の隅を白い影が過ぎった。 「―――ヒィィッ!?」 ビクッと身体が震え、同時に悲鳴が洩れる。あまりにも情けない声が、人気のない廊下に木霊する。 「い、今のは……?」 わざわざ独り言を口にする事で、膨れ上がってゆく恐怖心を必死に誤魔化す。 今さっき、確かに、教室の方に白い影が見えた――ような、気がした。 気がした、だけか。気のせい、か。 恐る恐る首を巡らすが、それらしきモノは何も見えない。 視界に入るのは暗い廊下と、並んだ教室の扉。そして廊下の先に非常灯の明かりが小さく一つ。 目の前の教室は――2年D組。男が担任を受け持っているクラスだった。 そうと知れば幾らか気持ちも落ち着いて、冷静さを取り戻してくる。 そもそも廊下と教室を仕切る窓は曇りガラスなのだから、中の様子が見えるはずもない。 恐らくは、車のヘッドライトか何かが映り込んだのを白い影と見間違えた。 そうだ、そうに違いない。 教室の中に何者かが居るなんて事は――そんな可能性は、決して、無い。 何をビクついている、さっさと確かめてしまえ。 そう己を叱咤すると、教室の戸に手を掛け一気に開ける。 ガラリ、と。戸を開けるその音がやけに大きく響いた。 「ほら、何も居ないじゃ……か……っ」 そこで男は硬直した。 教室の奥。 月の光の射し込む窓を背に、影が立っていた。 |

|
嗚呼、今夜は満月だったのだな。 先ず、そんな事を思った。だから結局、影の正体を認識するまでにたっぷり十秒、さらにその事実を理解するまでに数十秒を要した。 その影は、白い輪郭と仄青い陰から成っていた。 滑らかな曲線で描き出された細いシルエットは、大人の女と幼い少女が同居した、思春期特有の色香を漂わせる裸婦像。 月光の下で、文字通り透けるような白い肌と、真白く細い肩の上でサラサラと揺れる亜麻色の髪。 そして黒く大きな、勝気そうな瞳が、眼鏡のレンズ越しに男を見据える。 軽蔑するような、揶揄うような、それでいて甘く蠱惑的なその視線の主は。 月の光を逆光に尚輝く、少女――裸身の、女。 ゴクンッ 唾を飲む音がやけにハッキリと聞こえた。 鼓動が速くなり、ドクドクと心臓が脈打つ。 幻覚でも、見ているのだろうか? 男は己を疑わずには居られなかった。 こんな事がある筈が無い。いや、あって良い訳が無い。理不尽だ、不可解だ。妄想にしても程度が低い。脈絡が無い。そうだ、己は疲れてるんだ。疲れて、眠って、それで夢でも見ているに違いない。これは夢だ。きっと、夢に違いない。 夢の少女が微笑んだ。 妖しく、美しい旋律が耳をくすぐる。 「ねぇ、どうしたの先生?」 先生?先生だって? 男は一頻り混乱した後、漸く言葉の意味を理解した。 それは――己の事か。この学舎で、教鞭を取る己の事か。だが何故、夢の少女にまでそう呼ばれなければならないのか? 今一度、少女を視る。 両者の視線が絡み合った。 そうだ、この瞳には見覚えがある。 その、首筋を その、肩を その、手を その、脚を 覚えて、いる。否、良く、知っている。 何よりその裸身は、それこそ、夢にまで見た―― 「ひっ――」 記憶と認識が、結合する。 嗚呼、この少女は。 「ひ、が……の? 日向野、か? どうして、お前……」 くすくすくす、少女の笑い声が奇妙に木霊する。 少女の名は――日向野小春。 彼の教え子であり、学内でも有名な双子の、その片割れ。 成績は中の上。運動神経は抜群で、陸上部に所属しインターハイ出場経験も持つ。性格は至って明朗快活。先輩後輩、男女の別無く人気があり、やや落ち着きが無く素行が問題視される事もあったが、概ね教師達の評判も良い。 その彼女が、何故、こんな―― 「あたし、知ってたんだよ?先生」 知ってる?何を、何を知っている? くすくすくす、彼女は笑いながら続ける。 「先生、いっつもあたしの事見てたでしょ?いやらしい目でジロジロ、あたしの胸とか脚とかばっかりさ」 レンズの向こうで黒い瞳が意地悪く細まり、その視線で男を捕らえる。 男は動けない。反論出来ない。 まるで蛇に睨まれた蛙のように。 全て図星だった。授業中も、放課後も、いつもいつも、見ていた。見つめていた。否、見つめていたなどと言う表現は生温く、不正確だ。 視姦していた。 視線で彼女を、彼女の肢体を犯し、その姿態を嬲る様を妄想し、そして幾度となく己を慰める。 それは決して、他人に知られてはならない己だけの秘密。歪んだ悦楽。 それなのに、少女は男を糾弾する。 誰も知らない、己しか知らない男の秘密を。 選りにも選って彼女自身が。 「い――いつから、気付いて……いや、待て。待て待て待て。これは夢だ。私の見ている只の夢だ、そうだろう?そうでなければ、こんな――こんな事ある筈がない!お前が知って、知る筈は無いんだ!」 「夢かどうかなんて、この際、関係無いと思うけどな。ねぇ、先生?ここに居るのは、あたしと、先生の、二人だけ。そう、二人っきり――他には、誰も。誰も居ないんだよ、先生」 呪文のような言葉が、世界に染みる。男に浸み込む。 少女は窓際から離れると、手近な机の上に腰掛けた。 これ見よがしに組まれたその脚の、白い太股の隙間からチラチラと淡い茂みが覗く。男は、視線を逸らせない。魅入られたように、だた、食い入るように。 あぁ――あの、奥に。彼女の、あの―― 「そう、ソレ。その目だよ先生。その、いやらしい目でいつもいつも……気付かない方がどうかしてると思うけど?それに、ね。先生。あたし……あたしも、ね。先生に視られて、感じてたんだよ?今だって、ホラ……」 細く引き締まった脚がゆっくりと開き、脚の付け根の、密やかな茂みの下にある花弁が露になる。彼女の指が閉じた花弁にそっと触れると、焦らすように其処を広げてゆく。薄紅に染まった花弁は月の光を受けて妖しい光沢を帯び、その奥の深く清廉な蜜壷から滾々と湧き出す雫が、彼女自身をしとどに濡らしている。 「先生に視られて、こんなになってるんだよ?ホラ、クリトリスがこんなに腫れちゃって……オマンコの穴もグチョグチョで、もう、指だけじゃ物足りないの――ねぇ、先生。ダメだよ、視てるだけじゃ、視られてるだけじゃ――もう、我慢できない……欲しい、欲しいよ。先生のチンポが欲しくて堪らないの。先生の太いチンポで、オマンコ穿られて、ぐちゃぐちゃに広げて掻き回されたいの。先生の、臭くて熱い精液が欲しいの。お腹一杯、子宮から溢れるぐらい……ねぇ――先生。お願い、先生。 先生を――頂戴?」 ブツリ、と。 男の中で何かが切れた。あるいは、崩壊したのか。 男は意味不明の雄叫びを上げたかと思うと、少女に圧し掛かった。獣欲の赴くまま、柔肌に爪を立てては乳房を弄び、唇にしゃぶりついては口腔を貪り、少女の裂け目に己の股間を押し当てては擦り付ける。 もどかしい、もどかしい、もどかしいッ! ズボンの下で痛いほど勃起し、今にも張り裂けんばかりの怒張を漸う取り出すと、既に濡れそぼっている少女の中心目掛けて突き刺した。 少女が歓喜に咽ぶ。 「あはっ、先生……凄ッ!!」 何度も、何度も。何度も何度も腰を打ち付け、引き抜いてはさらに力強く衝き入れ、幾度と無く彼女の奥で精を放ち、溜まりに溜まった欲望を吐き出し続ける。膣内を白く汚し、胎内を白で穢し、それでも少女の中に納まり切らず、溢れ出した精液が周囲に飛び散り、少女と男の下半身を白い汚濁が染め上げる。 止まらない、止まらない。 少女の身体は、その内部は、妄想のソレなど到底足元にも及ばないほど素晴らしく、男は歓喜と官能に身震い悶え、絶え間無く襲い来る射精感に酔いしれる。そして少女もまた男を、男の分身を欲し捕らえ、淫らに咥え込み貪欲に虜んで放さない。放そうとしない。 決して離してなるものかと。 「ねぇ、先生。あたしの中、そんなに気持ち好い?」 ガクガクと、まるで壊れた玩具のように首を振って答える。 「ねぇ、先生。これで満足?」 ガクガクガク、何度も頷く。 「ねぇ、先生。もう思い残す事は、何も無い?」 ガクガクガクガクッ……え? ――空気が、変わった。 男の中で、生存本能とでも言うべき部分が警鐘を鳴らす。 何だ、一体何が起きて――起こっている?何かが危険だ、危険危険危険ッ――だが、それは何だ? 「ねぇ、先生」 組み敷かれたままで、少女が、ニィっと笑う。 あまりに淫らで、あまりに邪な、十代の少女とはかけ離れた笑み。男は違和感を覚えずには居られない。これは、何だ?彼女は一体――誰だ? 「あたしって優しいでしょ、慈悲深いでしょ?ねぇ、先生。あたしの膣内にいっぱい、こんなにいっぱい濃いのを出して……夢だったんでしょ?叶って良かったわね、先生。もう、悔いは無いよね?」 強烈な悪寒が、男の背筋を駆け上る。先程まで火照っていた身体は急激に冷え、ガタガタと震えが止まらない。 『ケケッ、ケケケケケケケケケケケケッ』 笑っている。背後から、笑い声が聞こえる。何者かがそこに居て、笑っている。 誰が、いや何が、居る?そこに、居る? 首が回る。彼の意志とは無関係に、背後を振り返る。それは、きっと、見たくない、見てはいけない、ハズなのに。 そして男は、見てしまった。 ああ、笑っている。それは確かに、笑っていた 少女から伸びた、長く長く伸びた影が。教室の壁に映し出された、黒い影が まるで影絵のような、それが、その影が 口を開けて、笑っている 『ケケケケケケケケケケケケケケケケケケッ!!』 何だ、コレは。一体、何が、どうなって 「うあぁぁあぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁぁッ!?」 ◇ 「なぁ、知ってる?」 「何を?」 「ウチの担任、夕べから行方不明なんだって」 「うっそ!?マジで?」 「あっ、それ私も聞いた。昨夜は宿直当番だったらしいんだけど、そのまま消えちゃったんだって噂」 「またかよ……これで何人目?」 「確かA組の子と、3年の先輩と、1年の子と……で、ウチの担任」 「今月に入ってもう4人かよ、家出や夜逃げが流行ってんのか?」 「知らないよ、そんなの……」 「ねぇ、小春はどう思う?」 突然話を振られた少女は一瞬、驚きに目を見開き、小首を傾げ肩を竦める。 「さあ?でも、何だか気味が悪いわよね」 そうだな、そうよね、と相槌を打つクラスメイトの皆は気付かなかった。 小春と呼ばれた少女の口元が、微かに歪んだのを。 くすくすくす。 『ケケケケケケッ』 |
外道士TOPへ