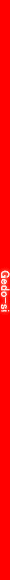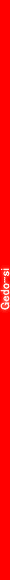
第四話「過去は記憶の残像」
―2―
|
「吉永!おい、吉永狩摩っ!聞いてるのか?」 自分の名を呼ぶダミ声で、私の意識は現実に引き戻された。教壇に立った中年教師が苛立った様子で黒板を叩く。 「吉永っ!授業中に何をボケーッとしてる。昼寝の時間はとっくの昔に終わってるぞ!さっさと前に出て来て問題を解け!!」 無言のまま立ちあがると、教室中の視線が私に集中する。 皆が皆、クスクスと笑ったり疎ましげな視線を投げかけて来るが、それもいつもの事だった。 「先生」 自分では随分と抑えて言ったつもりだったが、どうしても苛立ち混じりの不機嫌な声になってしまう。 私は教師の顔を見て―――睨み付けてるようにでも見えるのだろう、教師の顔が引き攣っている。 「……今日は体調が悪いので、早退します」 それだけ言うとカバンを手に取り、呼び止める声を無視して早々に退室した。正直、授業を受けるような気にはなれなかった。何故なら今日は…… 郊外のとあるマンションの501号室。それが私の住んでいる部屋だった。 『烏丸鴉也子(からすま あやこ)』と言う表札の隣に、少し小さな字で『吉永狩摩(よしなが かるま)』と私の名前が書いてある。私はカバンの中から部屋の鍵を取り出し、ロックを外してドアを開けた。 「ただいま」 「狩摩?早かったのね」 中に声を掛けると案の定返事が返ってきた。鴉也子姉さんはフリーのライターで、自宅で仕事をしている事も珍しくない。今はノートPCに向かって原稿執筆の最中のようだった。 「ちょっと狩摩、こっちに来なさい」 「……何?」 「貴女また、授業サボったんですって?さっき学校から連絡があったわよ」 「ごめん」 「『ごめん』じゃなくて」 世話が焼ける、と言わんばかりに一息ついてから、姉さんは続ける。 「誰が学費出してると思ってるの?なんて恩着せがましい事を言うつもりは無いのよ。けどね、高校ぐらい出ておかないと今時、ロクな仕事も見つからなくなるわよ」 あの事件の後、施設に預けられていた私を引き取って、今まで育ててくれたのが鴉也子姉さんだった。以前、父の世話になった事があってその恩返しと言う事らしいが、彼女の重荷にはなりたくないと、私は思っている。 「学校の授業なんて退屈なだけだし、それに私には……やらなきゃいけない事があるから」 「やっぱり、復讐するつもり?」 表向き、私の両親は事故死と言う事になっている。彼女は真相を知る数少ない人物の一人でもあった。 彼女の問いに私は沈黙で応える。今更、訊かれる事でも無かったからだ。 「あなたがそう決めたのなら、私に止める権利は無いわ。でもそれで、復讐が終わったらどうするつもり?一生を復讐に捧げるつもりじゃ無いでしょう?亡くなったご両親だって、あなたが幸せに……」 「ごめん」 強制的に話を切り上げる。姉さんの言いたい事は良く分かる。でも、理屈では分かっていても、納得は出来ない。私はそれほど物分りが良くないのだ。 自室に戻り、ベットの上にカバンを放る。着替えようとスカーフに手を掛けて、思い直した。制服のままでも別に問題は無いだろう。それより今は、時間が惜しく感じられた。 そのまま家を出ようとすると、姉さんが声を掛けてきた。 「私も、一緒に行こうか?」 「ごめん。今日は一人にして」 「そう……気をつけてね」 後ろ手にドアを閉め、家を出る。どうしてだろう、今日の私は謝ってばかりだ。今日が特別な日、だからだろうか。 そう、今日は父と母の命日。あの日から数えて今日で丁度10年になる。 途中で花屋に寄り、母が好きだった花を買うと、私は両親の眠る墓地へと向かった。 街外れの小高い山の上に位置する寺。その墓地に両親は眠っている。 寺の山門へと続く石段の下に立って上を見上げると、急勾配の石段はまるで灰色の壁のように目の前を塞ぎ、その両側に鬱蒼と生い茂った木々が陽光を遮り、周囲に暗い陰を落とす。 まるで異界への入り口のようだ、と思った。 寺社と言うものは本来、世俗とは切り離された世界である。そんな感想も持つことも、あながち的外れでは無いのだろう。敷地に一歩足を踏み入れただけで、周囲の音はまったく聞こえなくなり、時間の流れから取り残されたような不安を覚える。毎年通っていても、この奇妙な感覚には慣れない。 心に違和感を抱えたまま、私は一歩一歩ゆっくりと石段を登って行った。 石段の半ばに差し掛かった頃、私はふと、この違和感の正体に思い当たった。何故今まで気付かなかったのだろう、これは結界だ。人の心に働きかける事により『近寄りがたい』雰囲気を与え、不要な闖入者を拒む効果を持つ、決して強固な結界ではないが、高度な結界には違いない。誰がこんなものを?ここの住職が? ……だが何のために? 寺社それ自体は一種の聖域であり邪なる者を拒む結界である。が、人間を拒む理由はない。 「理由なら、あるぜ」 突然、頭上から声が降ってきた。まるで私の心の中を見透かしたように。 ハッとして声の方を見上げると、今まで誰も居なかったはずの場所に、黒い影が佇んでいた。 黒く長い髪、黒いコートのその姿は、10年の歳月を経ようとも変わる事はなかった。それどころか、瘴気とも言えるような更に禍々しい雰囲気を纏っている。 「よう、久しぶりだな。狩摩」 旧友にでもするような、気軽な挨拶が余計に私の精神を逆撫でする。その声、その姿、その顔。この10年間、一時足りとも忘れた事はない。人の姿をした、人を喰らう野獣のようなこの男を。 「九鬼いぃぃぃぃぃぃぃ!!!!!」 腹の底から、喉を震わせて絶叫にも近い声が放たれる。一瞬、それが自分の口から出たとは信じられない程の声が。だが、そんな事を考えるよりも速く体が動いていた。 「よう、久しぶりだな。狩摩」 九鬼は目の前に立つ、セーラー服姿の少女に声を掛けた。 いや、少女と言うのは正確では無いだろう。170cmを超える長身はモデルと言っても通用しそうなほどで、スラリと伸びた細い手足が引き締まった肢体を想像させ、風に揺れる長く艶やかな黒髪の、その隙間から覗く物憂げな表情の中で強固なまでの意志を宿した瞳が輝いている。儚さと気高さと、そして強さが同居した、薔薇の華の如き美しさ。それでこそ10年待った甲斐があったと言うものだ。 「九鬼いぃぃぃぃぃぃぃ!!!!!」 空気をビリビリと震わせながら、少女は拳を振り上げ九鬼に躍り掛かる。だが男にとって、少女の動きはスローモーションにも等しかった。細い腕を難なく掴んで捻りあげると、小馬鹿にしたように口元を歪める。 「ははっ、随分デカくなったじゃねぇか。あの頃はあんなにチビだったのによ。しかし殴り掛かってくるとは思わなかったなぁ……とんだお転婆に育ったモンだ」 「く……そっ、放せっ!!」 |

|
少女は男の腕を振り解こうともがく。平均的な16歳女子と比べれば体格も腕力も段違いの彼女だったが、九鬼が相手ではその絶対的な腕力差を埋めるには至らない。 「この、このっ!放せ、放せぇっ!!」 「ほらよ」 「きゃっ!?」 突然右腕を解放された少女の身体はバランスを崩し足場の悪い石段の上でフラつくが、持ち前の運動神経で何とか踏みとどまる。間違って転がり落ちれば、怪我では済まない。 「おいおい、危なっかしいなぁ……で、次はどうする?まさか今ので終わりか?」 九鬼がせせら笑う。が、男のあからさまな挑発は逆に少女を冷静にさせた。深呼吸して精神を落ち着かせる。相手は父を倒した男だ、無闇に挑みかかっても勝ち目はない。 狩摩はスカートの中に手を突っ込むと、裏地に縫いとめてあった呪符を素早く取り出した。非常事態に備えて常に携帯していたのは幸いだったが、あいにく手持ちの呪符はこれ一枚しかない……いや、この一枚があれば十分だ。少女は意を決すると呪符に気を込め、それと同時に口から、可聴域の限界とも思えるほどの高い音が発せられる。 時に速く、時にゆっくりと、歌うようなその旋律はやがて一つの形を織り成していく。 それは呪符の発動呪文。 狩摩の声に合わせて呪符が光を放ち始め、呪符に織り込まれていた呪式が解凍される。呪符が放つ光の軌跡が、まるで意志を持ったように動き、空中に複雑な文様―――西洋魔術における魔法陣にも似た図形を描き出していく。 そして、それが完成した瞬間、魔法陣の中心から異形の影が姿を現した。女性を模した流線形の体を金属光沢の装甲で覆い、二対存在する細い腕の先に、それぞれ異なる魔力の光を宿した戦闘人形。 その名は『式神・四天童子』 それを見た九鬼の口元が歪み、自然に笑みを形作る。 「父親のお下がりでオレに勝つつもりか?忘れたわけじゃぁ無いだろう、そいつはオレがあの時……」 「黙れっ!!」 九鬼の言葉を遮り、狩摩が叫ぶ。 「私はっ!この時のために、貴様を倒すためだけにこの10年間、生きてきたんだ!父と母の仇、討たせてもらう!!」 「面白れぇ……」 九鬼の顔に凶悪な笑みが浮かぶ。 「やってみろ!やれるモンならなッ!!」 |
外道士TOPへ