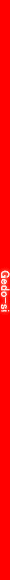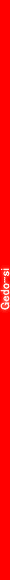
第四話「過去は記憶の残像」
―1―
|
私は、あの時の事を思い出していた。 あの忌まわしい日の出来事を。 もう10年前になる。偉大で、優しくて、私の世界の半分を占めていた父。幼い私には父の仕事を正確に理解する事は出来なかったが、まるで魔法使いのようだと、そう思っていた。 「わたしも大きくなったらお父さんみたいな魔法使いになるのっ」 そう言った私を、細い目をさらに細くして笑い、やさしく頭を撫でてくれた父。 「いいかい?狩摩、父さんはただの魔法使いじゃないんだ。恐ろしい怪物から弱い人達を守る為に戦う、正義の魔法使いなんだよ。だから、普通の人よりも危険な目に合う事が多い。それでも狩摩は魔法使いになりたいのかい?」 そんな父の言葉に、どう答えたかは今でもはっきり覚えている。 「うん!かるま、お父さんと一緒なら恐くないもん!!」 その日から父は、少しずつ『魔法』を教えてくれた。父と共に人々を護り怪物と戦う、その情景を夢想しては心躍らせた日々。 だが、楽しかった記憶は長くは続かない。 あの日、あの時。父は一人の男と対峙していた。父はその黒衣の男に向かって何か怒鳴っていた。言い争いをしているようだったけど、私には二人の諍いの原因に心当たりも無ければ、会話の内容も聞き取れない。 ただ、二人の間に険悪な空気が漂っているのだけは分かった。 お互いに一歩も引かない二人は、やがて無言で相手を威圧する。テレビで観た決闘シーンのようだ、とその時は思ったが、あながち的外れな感想でも無かったらしい。二人はほぼ同時に懐から紙切れを取り出す。それが『呪符』と呼ばれる物であることを、私は父に教えられて知っていた。 次の瞬間、轟音と共に閃光が走り、炎が舞い上がり、突風を巻き起こし、地が割れた。 その衝撃に、二人から随分と離れていたはずの私の小さな体は吹き飛ばされ、そのまま大地に叩き付けられる。 全身を襲う痛みに泣き出しそうになるのを堪え、私は顔を上げて二人が立っていた方向を見た。 一体何が起こったのか、経過こそ分からなかったがその結果が、今目の前に広がっている光景だった。 まず目に入ったのは先程と変らず立っている黒衣の男。そこを中心として大地がえぐれ、木々は薙ぎ倒され、さながら爆発でも起こったような有り様だった。 そして もうもうと立ち込める土煙の向こうに 地に伏した 父の姿を 見つけた 「お父さんっ!!」 そう叫んだつもりだったが、声が出ない。体もほとんど動かない。それでも、父の安否を確かめたくて、這いずるようにして父の元へと向かおうとしたその時、男の手に何かが握られているのが見えた。 黒く輝く棒……いや、剣。 剣を手にした男は、それを頭上に振り上げると倒れた父に向けて一気に――― だがその寸前で男の手は止まった。突如飛び出した影が倒れた父を庇うように覆い被さって来たのだ。飛び出して来たその影は、母だった。私と同じように何処かで二人を見ていたのだろうか、父が危機に直面している事を知った彼女は形振り構わず二人の間に割って入り、我が身を賭しても父の命を護ろうとしたのだ。私にはその時の母の気持ちが痛いほど良く分かった。出来ることなら、自分もそうしたいと思っていたのだから。 剣を振り下ろす格好で手を止めていた男は、邪魔だと言わんばかりに父から母の体を引き剥がすと地面に放り出し、その上に馬乗りになって母の服を剥ぎ取り始めた。 悲痛な母の悲鳴が、私の耳に届く。 母がどんな目に合っているのか、幼い私には想像すら出来ない事だった。ただ『乱暴されている』程度の認識しか持っていなかったが、今にして思えばそれは始めて目にした性行為であり、かつ、母が陵辱されている姿だった。 どれほど時が経ったのだろうか、母に覆い被さっていた男は不意に立ち上がると再び剣を手に取った。そして地に伏した母に向かって無造作に刃を振り下ろす。絶叫と共に赤い飛沫が宙に舞い上がった。さらに男は、倒れた父に向けてもう一振り。再び赤い飛沫が舞うが、今度は何の声も聞こえなかった。 ただ、笑い声だけが そう、笑っていた。父と母を手に掛けた黒衣の男は、嬉しそうに、心底嬉しそうに、笑っていた。その姿は黒衣の悪魔か死神か、およそ人間の姿には見えなかった。 その男と、目が合った。 見つかった!だが逃げようにも、体が思うように動かない。ゆっくり、ゆっくりと男の足が近づいてくる。私も殺される。恐怖に捕らわれながらも男から目を離す事は出来なかった。どうしてこんな事が許されるのか、何故私たちが殺され、この男はのうのうと生きているのか。私は、許さない。父と母を奪ったこの男を許さない! 私は恐怖と憎悪の入り交じった目で、男を睨み付けた。絶対に、目を逸らしたりはしない。 「くっ、くくくく……」 そんな私を見て、男が笑った。初めは、子供の無力な抵抗を嘲笑っているのかとも思った。 「いい目をするじゃねぇか、狩摩。安心しろ、お前は殺さねぇよ。まぁ、ガキでもいいんだがな……」 男は私の側で立ち止まり、身を屈めて顔を近づけてくる。 「10年だ」 「?」 「10年経って、お前がイイ女になったらオレの所へ来い。抱いてやるぜ」 ゲラゲラと下品な声で笑うその男を、私は無言で睨み付ける。 「そんなに憎いか?仇を討ちたいか?くくっ……なら殺してみろよ。オレに勝てたら、だけどなぁ」 そこまで言うと男は立ち上がり、振り向かずに去っていった。一人取り残された私は、ただ、声を上げて泣く事しか出来なかった。 私はあの光景を一生忘れない、忘れられない。いいや、忘れてなるものか。 父の一番弟子だった かつては兄と呼んで慕った事もある 父と母の仇――― 『九鬼 馨』の顔を、私は一生忘れない。 |
外道士TOPへ