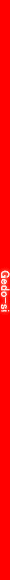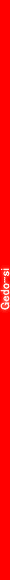
〜序章〜
―2―
|
「失踪事件の原因排除と、生存者の確保……か」 到着した館の前で、依頼内容を再確認する。 この館はとある富豪の別荘であり、数日前からまったく連絡が取れなくなった。 不審に思い何度か人を送ったが、帰ってくる者は一人としていなかった。 別荘で何か事件が起こっている事は間違いない。速やかに事件の原因を排除し、生存者がいる場合は身柄を確保すること。 「ふざけやがって」 あのデブ社長は“アナタに相応しい仕事”と言った。 退魔師である自分に相応しい仕事……つまりこの事件は妖魔絡みと言うことだ。だが、これだけの情報では妖魔関連の事件とは断定できない。意図的に情報を隠しているのは明らかだった。 普段ならばそんな条件下で仕事を受けることなど無いのだが、九鬼は依頼を受け、ここに居る。 つまりそれだけ、法外な報酬が魅力的だった訳だが、全てに納得した訳ではない。 「……ふざけやがって」 再度、呪詛のこもった言葉を吐きつつ、館全体を見渡す。 長い前髪とサングラスに隠れて気付かれにくいが、九鬼の顔の右半分は奇妙に歪んでいた。 おそらくは、過去に受けた何らかの傷が原因だろう。顔面の筋肉が引きつったままになっているのだ。 そして歪んだ顔面の上で怪しい光を放つ右眼は、義眼になっていた。 呪術的に作成された彼の義眼は魔力や霊力、妖気などを視覚的に認識する能力を備える、この世に二つと無い特注品である。 義眼を通して、この場に漂う妖気の流れを観察する。 「地下、か」 濃密な妖気の発生源を特定すると、ろくに注意も払わず館に進入した。 その館は、不必要なほどに豪勢な造りだった。 まるで映画に登場しそうな、ヨーロッパ貴族の屋敷をそのまま再現したような館の内部は、しかしその面影を殆ど残していなかった。数々の調度品はその殆どが無残に破壊され、床には巨大な獣が這い回ったような跡がありありと残っていた。 人の気配はまったく感じられない。 死体が転がっているにしろ、生存者が居るにしろ、全ては地下にある。 そう見切りをつけると、一直線に地下への入り口を目指す。 目指す場所はすぐに見つかった。 玄関ホールの正面、二階へと続く階段の裏にそれはあった。 地下へと続く階段。 その周囲の床が、下から凄まじい力で突き上げられたかの如く変形していた。 本来は、床がスライドして地下への入り口を隠す仕組みだったようだが、すでにその機能が失われていることは一目瞭然だった。 歪んだ鉄板―――地下への入り口を塞いでいたであろう物を見ながら呟く。 「意外と、厄介な相手かもな……」 階段の奥に注意を払う。妖気はその更に奥から流れ出ていた。 周囲に罠が無いことを確認すると、地下へと踏み込む。 九鬼が降り立ったそこは、明らかに異質な、異様な空間だった。 天井に備え付けられた電灯が弱々しく明滅し、地下の空間を照らし出している。 階段の終点、九鬼の立つ場所から通路が真っ直ぐに伸び、その両側には大きなガラスをはめた小部屋が並んでいた。 例えるならそれは、水族館に似ているかも知れない。 だがガラスの殆どは割れており、通路と部屋を区切るものは既に無かった。 部屋の一つに目をやると、その中に異形の影が見えた。 「いい趣味してやがるぜ……金持ちってヤツは」 それは奇妙に捻じくれた動物の死骸だった。 珍獣……と呼ぶにはあまりに奇怪なその姿は、奇形か、あるいは遺伝子操作の産物か。 どちらにしろ、ここの持ち主の趣味は相当歪んでいるようだ。 他の部屋も同様に、奇妙な生物の死骸が転がっている。 その中の一つに、九鬼は見覚えがあった。 実体を持った妖魔の死体。 以前倒したことのある、人肉を食らうタイプの妖魔である。 そのすぐ傍には、明らかにそれと分かる人骨が転がっていた。 「妖魔まで、飼っていやがったとはな」 つまりそれが、彼に依頼が回ってきた理由であった。 標的は、通路の突き当たり、一番奥の部屋を住処にしているようだった。 そこからより一層、濃密な妖気が噴き出してくる。 「……威嚇しているつもりか?」 どうやらヤツも、こちらの存在に気付いたらしい。 「さぁて、その面拝んでやろうじゃねぇか」 意識せず頬が歪み、その顔に笑みが浮かぶ。 そしてゆっくりと、奥へ歩いて行った。 通路の終点にあるその部屋は、他の部屋より随分と広い作りになっていた。 ちょっとした体育館ほどの大きさはあるだろうか。 その広い床の上には、白い繭が大量に転がっており面積の殆どを埋め尽くし、さらに部屋中に、太く、白い縄のようなものが縦横無尽に張り巡らされていた。 それが巨大な蜘蛛の巣であることに気付いたのは、ヤツが姿を現してからだった。 ―――死面蜘蛛。それがヤツの名だった。 人間よりも巨大な蜘蛛。特に蜘蛛が苦手でない人間でも寒気を感じるその異様。 だが、さらに異様なモノがその腹に浮かび上がっていた。 無数の人面。 その人面たちが一斉に苦悶の声を上げる。 断末魔が延々と続くような、おぞましく耳障りな声。 それは哀れな犠牲者の末路だった。 この妖魔は、粘性の糸で獲物(人間)を絡め取り、繭状の糸に封じて精気を吸い取る。 やがて精気を吸い尽くした獲物が死に至ると、蜘蛛の腹に人面が一つ増えることになる。 それが『死面蜘蛛』の名の由来である。 おびただしい数の人面が、犠牲者の数を物語っていた。 「ちっ」 思わず舌打ちする。 ヤツがいつからここで食事をしているかは分からないが、人面の数と繭の数を比較する限り、生存者は望めそうも無かった。 新たな獲物を見つけた蜘蛛の口が、キチキチと耳障りな音を立てる。 「よう、化物!間抜け共は美味かったか?」 声を掛けるが当然、返事があるわけも無い。 「何人食ったかは知らないが、食事の時間はここまでだぜ」 言いながら一歩踏み込むと、蜘蛛がじりじりと下がる。 「飼い犬に手を噛まれるようなマヌケの尻拭いをするつもりは更々無いが、これも一応仕事なんでな」 そう言うと、懐から一枚の紙切れ――札を取りだす。 奇妙な文字がビッシリと書き込まれたその札は、陰陽道で使用される言わば簡易魔法陣。 支配下にある式神を呼び出すための呪符である。 「さっさと……」 荒ぶる気が九鬼の体から吹き出し、妖魔を圧倒する。 「くたばりなぁっ!!」 |
外道士TOPへ