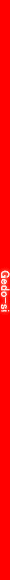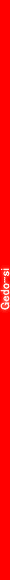
第六話「鬼は外道か、外道は鬼か」
―1―
|
「てぇりゃあああああぁぁぁぁぁぁっ!!!!」 それは悪夢の如き光景だった。 白と赤の布地がはためき舞うその度に、組の猛者が一人、また一人と倒されてゆく。 相手はただの一人、しかも素手。なのに十数人がかりで手も足も出ない。 「ゴルァアァ!!どこの組のモンじゃワレェッ!!」 怒号と共に、スキンヘッドの男が長ドスで斬りかかる。 大上段から一気に振り下ろされた一撃は、相手の脳天を西瓜のようにカチ割るはずだった。だがその直前で白刃はぐにゃりと軌道を変え、狙いが逸れた切っ先は床に深々と突き刺さる。 「――んなっ!?」 刃の側面に叩き込まれた平手打ち。それが刃の軌道を変えた正体だと気付いた時には既に遅く、男の眼前一杯に拳が迫っていた。 骨が潰れる異音を残し、ワイヤーアクションさながらに吹き飛ぶ巨躯。そのままの勢いで壁に叩き付けられた男の体は一度大きく痙攣したのを最後にピクリとも動かなくなった。 「あ、あっ、うああぁぁぁぁ―――っ!!」 パンッ 恐怖に耐え切れなくなった誰かが、とうとう発砲した。それを口火にして次々と銃声が上がるが、闇雲に放たれた銃弾は奴にかすりもせず、それどころか流れ弾で同士討ちになる始末。 「止めろ、バカッ!止めねぇかテメェらっ!!」 悲鳴と罵声が入り乱れるその狂乱の中で、奴は乱れ飛ぶ銃弾の雨を物ともせず、並み居る男達を次々と打ち倒していった。 悪い夢でも見ているのか。 相手はどう贔屓目に見ても、まだ10代。しかも巫女装束に身を包んだ、少女。 今や事務所に居た組員の半数以上が、その少女一人に倒されていた。しかも奴は全くの無傷。 「畜生っ……何なんだ、何なんだコレはよぉっ……」 藤木修治はデスクの陰に身を潜め弾雨をやり過ごしながら、だがどうする事も出来ずにただ呆然と、目の前で繰り広げられる現実離れした光景に見入っていた。 「後は、アナタだけよ」 それが自分に向けられた言葉だとは、思いたくもなかった。凛とした響きの中に少女らしいあどけなさを残したその声も、今この場で聞けば血も凍る死の宣告に等しい。既に悲鳴も怒号も銃声も止み、ただ屍の如く累々と横たわる組員と、僅かに息が残った者たちの呻き声。そしてその只中に佇む巫女装束の少女が一人。 「……いっ、一体何なんだ、テメェは?どこの組のっ、回しモンだ?おいっ……」 男はゆっくりと立ち上がった。カラカラに渇いた口から発する声に普段の張りは無く、手は嫌な汗でじっとりと濡れていた。だがしかし、相手がどんな手練であろうと、人間離れしていようとも、一方的にやられたとあっては藤木の名折れ。せめて一矢報いて――男は震える手で、目の前の少女へ銃口を向け、撃鉄を起こす。 「『始末屋』だよ」 銃を向けられてもまったく怯まない、挑むような少女の瞳と正面から睨み合う。 「ただ、頼まれただけ。アンタたちが弄んだ、女の人たちから……ね」 獲物に狙いをつける猛獣さながらの、その眼。 「へっ、へへ……何だよ、そりゃぁ。そんな理由で……コレか?なぁ、オイ。フザケんなっ!」 「悪人が裁かれるには十分過ぎる理由だと思うけど?」 「正義の味方でも気取ってんのかっ、手前ぇっ!」 ブツリと、男の中で何かが切れた。急激に膨れ上がった怒りが、得体の知れない少女への恐怖を吹き飛ばし男を突き動かす。 「手前ぇのやってる事も、犯罪にゃ変わりねぇんだよぉっ!このっ―――化け物があぁぁっっ!!」 引き金を引いた。 撃鉄が打ち下ろされ、雷管を叩き、火薬が発火。銃口が火を吹く――より迅く。瞬時に間合いを詰めた少女の拳が男の腕を跳ね上げる。肘がありえない角度に折れ曲がり、遅れて放たれた銃弾は見当外れの方向へと飛び去った。 「いっ……ぎっ、ぐ……っが」 苦痛に呻く男の喉を少女の手が捉え、そのまま片手で首を絞めながら男の体を宙に吊り上げる。 「――今、何て……言った?」 呟くような少女の問いには答えずに、男は宙吊りのまま蹴りを放つ。だが不自由な体勢ではただ足をバタつかせているに等しく、細腕から逃れる事すら叶わない。 男は再度、憎々しげに呻いた。 「……化け、物めっ」 「違うっ!!」 絶叫にも似た叫びを上げて、少女は吊り上げていた男の体を床に叩き付けた。倒れた男の上に馬乗りになり、無防備な顔面めがけて容赦なく、狂ったように拳を振り下ろす。 「違う違う違う違う違うっ!!アタシはっ、アタシは化け物なんかじゃないっ!!!!」 何度も、何度も。 何度も何度も何度も、殴る。撲る。グローブに包まれた拳を、叩き付ける。鼻がひしゃげ、顎が砕け、頭骨が陥没し、ビクビクと痙攣を繰り返す体が動かなくなるまで、ただひたすらに殴り続けた。漸く落ち着きを取り戻した頃には、少女の下に転がるソレは原形が判別不可能な肉の塊と化していた。 「はっ、はっ、はっ、は、はあぁぁ〜……また、やっちゃった…」 我を取り戻せば、流石にやり過ぎたかと自己嫌悪に陥る。昔から『化け物』と呼ばれると頭に血が上り抑えが効かなくなった。そして、彼女が本気で人を殴れば―――足元に転がる一際無残な骸が全てを物語る。 「まぁ、やっちゃった事は仕方が無いし……早いトコ退散、退散」 折りしもサイレンの音が近付いてくる。騒ぎを聞きつけた誰かが警察に通報したのだろう、引き上げの合図だった。 「……っと、いけない!忘れるトコだった!!」 彼女は死屍累々とした室内をグルリと見回すと、隅にあった金庫を目ざとく見つけ頬を緩ませる。 「んふふっ、『金に悪意は無い』ってね。有意義に使わせて貰いますよ〜♪」 小型とは言え、かなりの重量があるはずの金庫をそのままヒョイと肩に担ぎ上げ、少女は巫女装束を翻し足早にその場を去って行った。 ※ 「ふんふんふん〜♪」 アタシこと仁村麻紀(にむら まき)は、いつも通り巫女装束に身を包み、鼻歌交じりに境内の掃き掃除をしていた。調子に乗って小躍りしそうになるのは何とか堪えたが、顔がニヤけてしまうのはどうにもならない。傍目には気味悪く映るだろうが、心配は御無用。正月でも無いのに早朝から参拝に来る物好きなど居ないので、境内にはアタシ一人。見ているとしたら精々カラスぐらいだ。 で、何がそんなに嬉しいのかと言えば、先日持ち帰った金庫(当然、暗証番号が分からなかったので力尽くで抉じ開けた)の中に一千万単位の現金が入っていたのだ。 これぞ棚からボタ餅。予想外の収入に躍り出したくもなると言うもの。 だからちょっと奮発して、依頼完了の報告と一緒に依頼料の半分を返してあげたら泣くほど感謝された。これだから人助けはやめられない。人に感謝されるのはこの上なく幸せな気分だし、悪人共をぶっ飛ばしてストレス解消にもなる、まさに一石二鳥の仕事だった。 念のため自己弁護しておくなら、何も自分の為だけに『始末屋』などと言う稼業をやっている訳ではない。 例えば、他人を不幸に陥れ自分は甘い蜜を啜る輩。 或いは、現在の法では裁けない犯罪者。 そう言った連中を人知れず闇に葬る、言わば現代の『必殺仕事人』なのである。全ては世のため、人のため。 ……もっとも、始末するしないの判断は全てアタシの主観によるものだし、趣味と実益を兼ねた仕事である事は、否定出来ないけれど。 「あの人も、もう嫌な事は忘れて幸せになってくれれば、言う事無いんだけどね〜」 先日の暴力団紛いの連中は、女性を集団でレイプしてはビデオに録画し、それを無修正アダルトビデオとして売り捌き荒稼ぎをしていた小悪党共の、その総元締めだった。今回の依頼主である女性は、その犠牲者の一人である。 忘れろ、と言うのは無責任な話かも知れない。レイプされた事の無い人間に、彼女の気持ちが分かるはずも無い。それでも、復讐を果たした今、彼女には過去を振り払って新しい道を歩んで貰いたいと思うのは自分のエゴなんだろうか?とも思う。 「あ〜、もう!依頼人のその後なんて、アタシが気にしたって仕方ないじゃないっ!!止め止め。とりあえず予定外の収入もあったし、これでしばらくは遊んで暮らせるわ〜♪」 ……とか言いつつ、ここでバイトしている自分が居るのだけど。まあ、これは趣味のようなものだから良しとしよう。そんな上機嫌のアタシの元に新たな依頼人が訪れたのは、丁度昼食を終えた後の事だった。 「仁村麻紀さんですね?」 そう切り出して来たのは、羨ましいほどに綺麗な髪が特に印象的な、美しい女性だった。まるでシャンプーのCMに出てくるみたいな、艶やかな濡れ羽色の髪を腰のあたりまで伸ばして、普段はあまりお目に掛かれないような上品かつ高価そうなスーツに包まれた身体はファッションモデルもかくやと言う見事なプロポーション。立ち居振る舞いも外見に相応しく気品があり、まるで隙が無い。手にしたアタッシュケースが浮いてはいるが、あまりに完璧過ぎて嫌味すら感じない――人形のようだ、とも思った。 「え、えぇ。そうですけど……アナタは?」 「申し遅れました。私は、烏丸鴉也子(からすま あやこ)と申します。早速ですが貴女に折り入ってお願いしたい事があります」 前置きも早々に彼女は一枚の写真を取り出し、アタシの前に差し出してきた。 「この男を、始末して頂きたいのです」 そして刃物のように鋭い視線でアタシを正面から見据えながら、憎悪に満ちた声でこう付け足した。 「男の名は、九鬼馨。人の皮を被った外道です」 |
外道士TOPへ