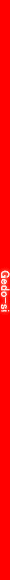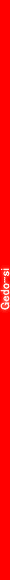
第三話「家族の肖像」
―1―
|
『……許さない』 麗らかな春のような日差しが窓から射し込む。 初夏とは言えども、避暑地として賑わうこの別荘地は実に穏やかな、過ごしやすい気候で、開け放たれた窓からは涼しげな風が吹き込みレースのカーテンを揺らしている。 その窓の、すぐ側の椅子に一人の少女が座っていた。 肩口で切り揃えられた癖のないストレートの髪に大きなリボン、フリルやレースを多用して、白一色に統一された服装が少女の幼さ、そして儚さをより強調しているように見える。 膝の上にクマのヌイグルミを乗せたまま、どこか寂しげな表情でぼんやりと外を眺める少女の髪が、風に揺れてサラサラと流れるように舞った。 しばらく窓の外を眺めていた少女が、何事か思い立ったように、ふと室内に視線を向ける。その先に居たのは、カンバスに向かう壮年の男。 少女から少し離れた所で、黙々と絵筆を走らせているその男は長身だが全体的に体の線が細く、柔和な顔はやや男らしさに欠け、いかにも優男と言った風体だった。女性的とも言えるその顔立ちは、良く見れば少女と似た面影があった。 「ねぇ……パパ……」 「もう少しだから、動かないで」 最後まで聞かずに言葉を遮る父に、少女が拗ねたように言う。 「……お外で、遊びたいな」 我がままを言う娘に苦笑しながらも、男の目は我が子を慈しむ慈愛に満ちていた。 「あと少しで終わるから、そうしたら一緒に湖を見に行こうか?」 「ホント!?」 少女の顔がパッと明るくなる。 「ああ、ここ最近はずっと家の中で勉強ばかりだったからね。たまには外に出るのもいいだろう」 「ありがとうパパ。大好き!」 ヌイグルミとギュっと抱きしめ、その後ろに隠れるようにして父を見上げる少女の頬は、気恥ずかしさのためか真っ赤に染まっている。 「パパも、夏生(なつき)の事が大好きだよ」 これ以上ないと言うほど、優しい微笑み。 「だから、もう少しだけ我慢して。すぐに終わるからね」 『……憎い……』 突然、爆音が鳴り響く。それがバイクのエンジン音だと気づいたのは、音が鳴り止み、家の呼び鈴が鳴らされた後だった。 「…………お客……さん?」 父娘二人の世界に突如現れた闖入者。 男は内心苛立ちつつも、娘の手前その感情を押し殺し、不安げな表情の娘を安心させるように出来るだけ普段通りの笑みを作った。 「そう、みたいだね……誰だろう?ちょっと見てくるよ」 大人しく待っているよう娘に言い含め、男が足早に玄関へと向かうその間にも、呼び鈴は止む事はなく急かすように鳴り続けている。 「はいはい!今出ますよ!!」 あまりの喧しさに辟易しつつ、玄関の戸を開けるとソコには―――黒い影が、視界を遮るように立ち塞がっていた。 玄関先に立つ、見上げるような長身のガッシリした体格の男。全身黒ずくめのその男が、丸いサングラスの奥に隠れた眼でこちらを見下ろしていた。例え見えずとも確かに感じる鋭い視線が痛いほど全身に突き刺さる。 「……あんたが、加納龍秀(かのう たつひで)か?」 黒衣の男の口が開き発せられたのは、外見に違わぬ凄みのある野太い声。そのあまりの威圧感に、一瞬、背筋に怖気が走った。 「そ、そうですが……貴方は?」 男の迫力に気圧されぬように、精一杯の虚勢を張る―――が、声が震えるのを抑えるのがやっとだった。 「ああ、オレは金(チン)の代理人だ。約束の絵を引き取りに来た。」 金道福(チン・タオフー)。それは確かに彼のパトロンの名だったが、だからと言って「はいそうですか」と素直に頷けるような状況では無い。それに…… 「以前お会いした代理の方は、女性の方でしたが?」 「あの女も、案外忙しいらしくてな。くくっ……警戒してるのか?用心深いのは良い事だな」 黒ずくめの男は手に持っていたアタッシュケースを目の前にちらつかせる。まるで重さなど感じていないかのような仕草だ。 「金ならちゃんと預かってる。心配するな」 言いながら黒衣の男はズカズカと家の中に入り込むと、物珍しいとでも言いたげに周囲を見渡す。屋内のあちらこちらに飾られ、あるいは乱雑に置かれた絵の数々を眺めながら時折「へー」とか「ほー」と感嘆の声を漏らしている。 「コレは、全部アンタの作品か?描いてあるのは、アンタの娘か?」 「ええ、そうですが……」 男が眺めていたのは『娘』と題された一連の肖像画だった。背景の殆どは屋内―――恐らくはこの家の中の何処かなのであろう。加納龍秀と言えば、数年前に妻を亡くしてからは娘と二人で別荘地に移り住み、それ以来娘の肖像画ばかり描いている事で有名な、変わり者が多いと言われる絵描きの中でも変人で名の通っている画家だった。 「オレは絵に関しては素人だが……金の野郎が欲しがるのも分かるな」 この男は金の依頼を受け、代理として訪れたのでは無かったか。依頼主を野郎呼ばわりするとは、一体どういう神経の持ち主なのか? 「絵には色んなモンが籠る。特に人物画は、描き手や描かれた人物の想い、その時の感情、様々なモノが一緒に塗り込められる……特にアンタの絵はそれが顕著だな」 『……恨めしい』 壁に掛けられた絵を眺める男の目が、サングラスの下で細く、笑みを形作ったのを加納は気付かなかった。 「技術的な事は分からんが……いい絵だ。オレも一枚ぐらい欲しいね」 「は、はぁ……そうですか」 男の言わんとする事が飲み込めず、加納は曖昧な返事を返すしか無かった。 「……で、本題に入ろうか。金が注文した絵はどれだ?」 「それは丁度、今描き上げているところです。明日までには完成する予定ですが」 「一日早かったと言う訳か……それじゃあ、また明日の朝にでも出直して来るわ」 男が踵を返し玄関へと足を向けたその一瞬、奥の部屋の入り口からこちらを覗いていた少女と目が合った。途端に少女は、サッと素早い動きでドアの影に隠れ、今度は頭だけを出して恐る恐るこちらの様子を窺っている。一目見ただけでも分かった。先ほどまで眺めていた絵に描かれている少女―――加納龍秀の一人娘、加納夏生である。 「夏生、お客さんにご挨拶は?」 「ああ、いいって。気にすんなよ。」 男の口元が不気味なほどに釣りあがり、笑みと呼ぶにはあまりに凶悪な面相となる。 「すみません。人見知りの激しい娘で……」 「可愛い娘じゃねぇか……精々大切にしなよ。じゃあ、オレはまた出直して来るわ」 「はい、それではまた明日」 大股で玄関を出て行く男を見送る加納の背後に、刺すような視線を投げかける存在が居た事に気付いた者はまだ居なかった…… |
外道士TOPへ