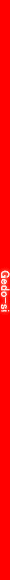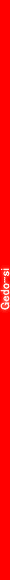
第一話「夜は無情に」
―1―
|
「すっかり遅くなっちゃったなぁ」 夜の郊外。人通りの少なくなった道を一人の少女が早足で歩いていた。 短く切った髪と勝ち気そうな顔立ちから、一見すると少年のような印象を受けるが、都内某私立高校指定の制服であるブレザーのスカートから伸びた艶やかな脚は、大人の女性特有の曲線を描いており、そのアンバランスさが彼女の微妙な年齢を体現していた。 普段なら周囲の目を気にして太股を隠そうとするのだが、今はそんな余裕は無かった。 少女は左手の腕時計に目をやると、その細い眉をしかめる。 PM10:38―――門限の時間はとっくの昔に過ぎていた。鬼のような形相で自分を待ち構えているであろう母親の姿を思い浮かべ、深いため息を吐く。 「もう、小春があんなこと言うから……」 帰宅時間が大幅に遅れる原因を作った友人の名を漏らす。 もっとも、無理に誘われた訳ではなく自発的に彼女に付き合ったのだし、しかもここまで帰りが遅くなったのは彼女自身が率先して遊び回っていたからなのだが……親への丁度良い言い訳になる。今回は彼女に悪役になって貰おう。 そう思いながら、家路を急いでいた。 しばらく大通り沿いに歩いていた少女は、突然道を逸れて大きな公園へと入る。 普段から通学にも使っている近道である。 だが夜の闇に支配され、人気の全く無い公園は、昼間とは異なる一種異様な雰囲気に包まれていた。 背筋に寒気を感じた少女は、早く公園を抜けようと自然と小走りになる。そんな彼女の視界に奇妙な物が写る。 すると先刻までの悪寒は鳴りを潜め、次第に好奇心が勝ってくる。元来、彼女は何事にも首を突っ込みたがる性質なのだ―――例え、好奇心が猫を殺すことになろうとも。 ふと足を止め、視界の角に写ったモノに近づいて行く。 それは女物の洋服だった。下着から靴までもが一通り、公園の片隅に無造作に落ちている。 「やだ……何これ、誰かのイタズラ?」 不審に思いながらも、手に取って確かめようと近づいたその時、少女の顔に水滴が落ちてきた。 「雨?」 だが見上げても、夜空には雲一つ見えない。 濡れた顔を拭き取ろうと袖を擦り付けるが、水滴と思っていたソレは異様に粘ついて顔を汚す。 「うげぇ、何よこれ……最悪」 仕方なく、ティッシュで拭き取ろうと鞄を開けたその時。 ベチョ 不快な音と共に、彼女の足に何かが触れた。 「きゃあっ!?」 その不気味な感触に思わず悲鳴を上げる。 足に絡み付いて来たソレは、大きな粘液状の塊だった。 外灯の明かりに照らされて、ヌラヌラと灰色に光る塊は、まるで意志を持っているかのようにゆっくりと少女の脚を這い回る。 「やだっ、やだっ!!何よコレぇ!?」 必至に引き剥がそうとするが、まったく手応えが無い。それどころか、引き剥がそうとしたその手にも、粘ばつくモノがべっとりと張り付く。 「やっ……誰か、誰か助けてぇ!!」 助けを求め、公園の外に駆け出そうとしたその時 ベチャ、ベチャベチャベチャ 周囲から、何かが跳ねるような、粘つく水音のようなものが聞こえたかと思うと、少女の身体に粘液状の物体が次々と飛びついてきた。腕に、太股に、首筋に、胸に、次々と張り付いてくるソレは、徐々に少女の身体を覆い、そして服の下に潜り込んでくる。 「っ………………!?」 恐怖のあまり絶叫をあげようとしたが、その口も既に粘液によって覆われ、塞がれていた。 それどころか、体中の穴と言う穴に粘液が入り込んでいく。 得体の知れない物体に肉体を陵辱される、そのおぞましい感覚に吐き気を覚えるが、既に喉は塞がれ、胃から逆流したモノは行き場を失い、粘液に消化吸収されていく。 少女の口から漏れるのは、声にならない苦しげな鳴咽だけであった。 粘液状の物体が身体の内外を這い回り、肉体が侵食されていく異様な感覚。 既に顔はすべて塞がれ、五感の殆どは機能を果たさず、さらに耳から侵入した粘液が三半規管を侵し、平衡感覚すら失った少女には、触覚から強制的に送り込まれて来る気が狂う程の異様な感覚に身を委ねる他、術はなかった。 まだ男性を受け入れた事の無い花弁を、引き裂くようにして侵入した粘液の塊は、膣内を押し広げながら奥へと進んでいく。 やがて子宮口に達すると、それすらもこじ開け胎内へと侵入する。 同時に菊座からも粘液が入り込むと、蠕動運動に逆らって腸内を上っていく。 凄まじいまでの圧迫感が少女を襲う。 ―――苦しい。 だがそれでも、痛みはまったく感じない事が恐ろしかった。 やがて少女の体内外をすべて覆い尽くした粘液状の物体は、その肉体を消化し始める。 四肢が、肌が、あるいは内側から身体が溶け出していく、その想像を絶するほどの恐怖。そして絶望。 (ああ、消えちゃう……わたしの身体が……無くなっちゃう……) 生命活動を維持するのが不可能なほどに肉体が消化されても、それでも少女の意識は残っていた。 痛みを感じる事なく身体が消滅していくという、その現実感の無さは、さながら悪夢の中の出来事のようだった。 (やだよ……こんな夢……。誰か、早く起こして……マ、マ……) そうして最後の肉の一片までもが消化されきった時、少女の意識は途絶えた。 少女の肉体を蹂躪していた物体は、食事を終えると小さく分裂し、ある物は草むらの陰に、ある物は地面の下へと消えていく。 後には残ったのは、少女が身に着けていた制服だけだった。 |
外道士TOPへ